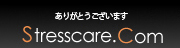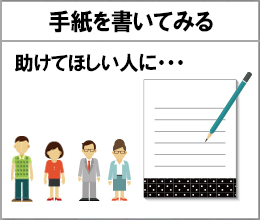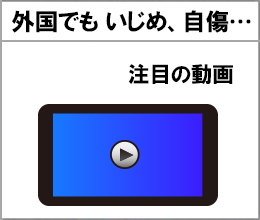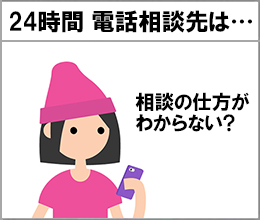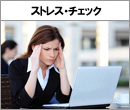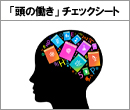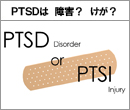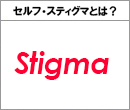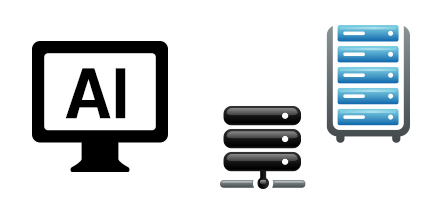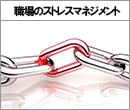新型コロナウィルス感染症で、健康面、職業面、経営面などで様々影響を受けた方々にお見舞い申し上げます。
感染症対策のため、日本法令様主催のセミナーは、会場開催を中止し、ビデオ対応とさせていただきました。
「ハラスメント 相談対応マニュアルの作り方 と 企業研修のコツ」のセミナー受講のみなさまは、日本法令ホームページで、ビデオ対応のご確認をお願いいたします。
追記 DVD販売決定! 同セミナーのビデオ講座が好評でしたので、アマゾンでDVDとして販売されることになりました。ご関心のある方は、アマゾンをご覧下さい。

施行日の政令が公布されました。
→ 令和元年12月4日 政令第174号(ダウンロード)
「パワハラ指針」が告示されました(令和2年1月15日)。
→ 令和2年 厚生労働省告示第5号(ダウンロード)
「セクハラ等改正指針」が告示されました(令和2年1月15日)。
→ 令和2年 厚生労働省告示第6号(ダウンロード)
通達「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8章の規定等の運用について」が発出されました(令和2年2月10日)。
→ (ダウンロード)
通達「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」が一部改正されました(令和2年2月10日)。
→ (ダウンロード)
通達「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」が一部改正されました(令和2年2月10日)。
→ (ダウンロード)
人事院規則10-16 パワー・ハラスメントの防止等(令和2年4月1日)。
→ (ダウンロード)
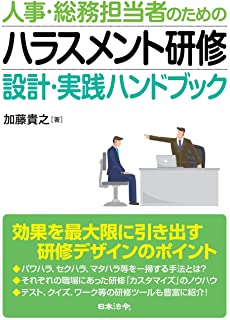
研修担当者向けのハンドブックを刊行いたしました。突然、研修担当に指名されても困らないように、誰もがカンタンにできる研修ノウハウを盛り込んでいます。おかげさまで重版となりました。大変ありがとうございました。
『上司が萎縮しないパワハラ対策』が売れ行き好調で、重版となりました。読者のみなさまのおかげです。大変ありがとうございました。本書の後継書として、2022年に中小企業版を発刊予定です。
多くのパワハラは「コミュニケーションの行き違い」が関係しています。
上司と部下のコミュニケーションが不足しているときや、上司から部下への一方通行のコミュニケーションのときには、「行き違い」が生じやすくなります。
「行き違い」は、上司の萎縮によっても起こります。
上司がパワハラと言われるのを恐れて必要な指導まで萎縮してしまうと、コミュニケーションが減ってしまい、かえって「行き違い」は生じやすくなります。
上司は萎縮することなく、部下へのコミュニケーションを増やし、また、部下の話を聞く機会も増やす。上司から部下へ、部下から上司への「双方向のコミュニケーション」を増やしていくことが重要です。
コミュニケーションの良い職場はおそらく誰にとっても働きやすい職場となります。風通しの良い、働きやすい職場づくりを目指すというのが「上司が萎縮しないパワハラ対策」です。
■『ビジネスガイド』(日本法令)2021年9月号
事例から学ぶ
失敗しないハラスメント相談対応ノウハウ
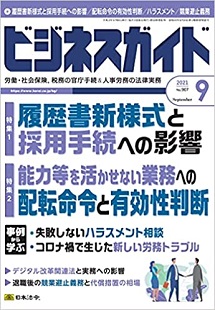
■『ビジネスガイド』(日本法令)2021年3月号
特集3
コロナハラスメントを防ぐためにできること
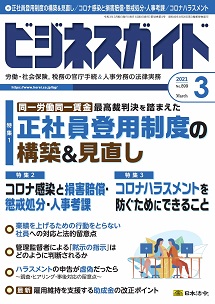
■『ビジネスガイド』(日本法令)2020年9月号
特集3 ハラスメント対応
「モジュール」を活用したパワハラ防止研修の上手な組み立て方

■『ビジネスガイド』(日本法令)2021年9月号
連載 ハラスメント相談室 第9回
ハラスメント相談担当者の人数
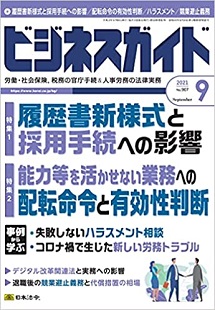
■『ビジネスガイド』(日本法令)2021年8月号
連載 ハラスメント相談室 第8回
初動対応の仕方を周知する
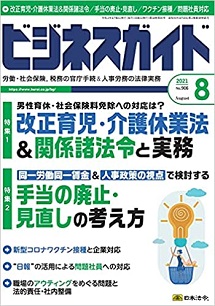
■『ビジネスガイド』(日本法令)2021年7月号
連載 ハラスメント相談室 第7回
若い人の間で起こるパワハラ
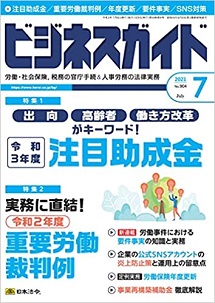
■『ビジネスガイド』(日本法令)2021年6月号
連載 ハラスメント相談室 第6回
新人1人ひとりの状況確認が必要な時期
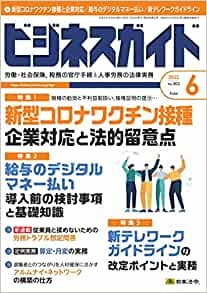
■『ビジネスガイド』(日本法令)2021年5月号
連載 ハラスメント相談室 第5回
ハラスメントの実態把握の方法
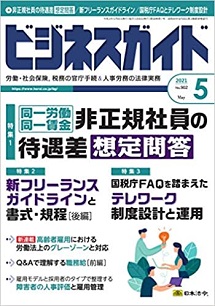
■『ビジネスガイド』(日本法令)2021年4月号
連載 ハラスメント相談室 第4回
ハラスメント防止にはどんなルールが必要か
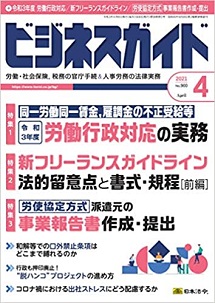
■『ビジネスガイド』(日本法令)2021年3月号
連載 ハラスメント相談室 第3回
経営者の理解を得るにはどうすればよいか
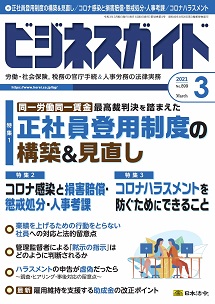
■『ビジネスガイド』(日本法令)2021年2月号
連載 ハラスメント相談室 第2回
パワハラ対策は何から取り組むべきか
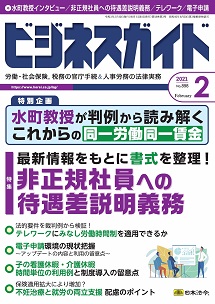
■『ビジネスガイド』(日本法令)2021年1月号
連載 ハラスメント相談室 第1回
コロナ拡大で研修ができない場合の対応
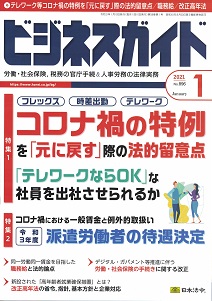
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2021年8月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 17
「視線を合わせて会話をしていますか?」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2021年7月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 16
「『お疲れさま』をタイムリーに使う」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2021年6月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 15
「高圧的な態度を取ると、何が起こり得るのか?」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2021年5月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 14
「『報・連・相』の『相談』を増やす」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2021年4月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 13
「『言い過ぎたかな』と思ったときの謝り方」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2021年3月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 12
「職場で『行き過ぎた言動』を見掛けたときは?」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2021年2月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 11
「ハラスメントを受けてしまったときの対応法」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2021年1月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 10
「パワハラは上司の生産性も低下させる」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2020年12月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 9
「『口癖』がトラブルになってしまうことも」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2020年11月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 8
「リモートワークで起こりやすいハラスメント(その2)」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2020年10月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 7
「リモートワークで起こりやすいハラスメント(その1)」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2020年9月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 6
「『双方向のコミュニケーション』がポイント」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2020年8月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 5
「周りの人の就業環境に気を配っていますか?」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2020年7月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 4
「パワハラ判断基準の「必要性」と「相当性」って何?」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2020年6月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 3
「部下から上司へのパワーハラスメントもある」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2020年5月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 2
「結果が出ない人には、プロセスに焦点を当ててみる」
■『コミュニケーション シード』(経団連事業サービス 社内広報センター)2020年4月号
連載 ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ 1
「行き違いがハラスメントを生む」
■『Play Graph』(プレイグラフ社)2020年5月号
特集 こじらせないためのパワハラ対策

■『月刊 人事マネジメント』(ビジネスパブリッシング)2020年8月号
連載 パワハラ「相談窓口」マニュアル
第6回(最終回) 判定後の対応、再発防止の手法
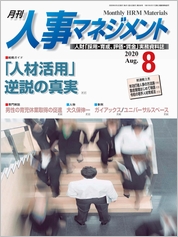
■『月刊 人事マネジメント』(ビジネスパブリッシング)2020年7月号
連載 パワハラ「相談窓口」マニュアル
第5回 パワハラ判定のポイント
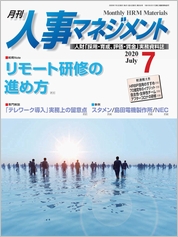
■『月刊 人事マネジメント』(ビジネスパブリッシング)2020年6月号
連載 パワハラ「相談窓口」マニュアル
第4回 行為者上司・第三者ヒアリングの進め方

■『月刊 人事マネジメント』(ビジネスパブリッシング)2020年5月号
連載 パワハラ「相談窓口」マニュアル
第3回 行為者ヒアリングの進め方

■『月刊 人事マネジメント』(ビジネスパブリッシング)2020年4月号
連載 パワハラ「相談窓口」マニュアル
第2回 被害者ヒアリングの進め方
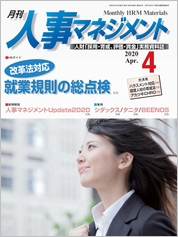
■『月刊 人事マネジメント』(ビジネスパブリッシング)2020年3月号
新連載 パワハラ「相談窓口」マニュアル
第1回 窓口設置と相談対応の流れ(全体像)
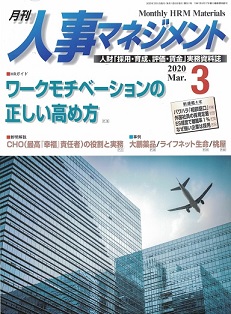
■『月刊 人事マネジメント』(ビジネスパブリッシング)2019年12月号
著者から人事担当者へのメッセージ
『上司が萎縮しないパワハラ対策』
クリックすると、記事をお読みいただけます。
■『中日新聞』『東京新聞』2019年11月16日朝刊
パワハラの特集があり、元バレーボール選手の益子直美さん、教育学者の坂越正樹さんとともに、弊社代表・加藤貴之のインタビュー記事を掲載していただきました。益子さんは、子供たちのバレー指導で「監督が怒らない」を提唱されています。
記事は、中日新聞(CHUNICHI Web)または東京新聞(TOKYO Web)でお読みいただけます。


■『週刊 教育資料』(教育公論社)2019年11月11日号
自著を語る 『上司が萎縮しないパワハラ対策』
コミュニケーションの改善がパワハラ問題防止のカギ
■『ジンジュール(労政時報の人事ポータル)』(労務行政研究所)2019年8月23日
BOOK REVIEW ―人事パーソンへオススメの新刊
『上司が萎縮しないパワハラ対策』
クリックすると、サイトをご覧いただけます。
■『ビジネスガイド』(日本法令)2019年8月号
特集1 パワハラ防止法成立!
パワハラ防止10の対策と「指導記録書」活用のススメ
クリックすると、記事をお読みいただけます。
日本法令様主催 「社労士様、人事担当者様向けセミナー」
 「パワハラ新法への対応」と課題解決型企業研修のコツ
「パワハラ新法への対応」と課題解決型企業研修のコツ
1 パワハラ対策の現状と課題
窓口設置(大企業、中小企業)、相談件数目安、無関心と過剰反応
2 カギを握る経営者・幹部の理解
組織の風通し、組織コミュニケーションと経営判断の関係
3 パワハラとセクハラの対応スキームの違い
「行為者の上司」がパワハラ問題解決のキーパーソン
4 厚労省マニュアルからみた『7つの準備』
人事部門が対応すべきこと(7つ)、社労士等による支援(3つ)
5 パワハラ新法と就業規則・規程策定のポイント
パワハラと判断できない場合の規定、監督責任の規定等
6 どのような研修が必要とされているか?
標準研修とポイント、ディスカッション、課題対応へのカスタマイズ
7 ケースからみた「対応のポイント」
相談対応のフローチャート確認、ケース対応のポイント
■出版記念 2019年8月5日(終了)
■追加開催 2019年8月23日(終了)
■追加開催 2019年9月9日(終了)
■追加開催 2019年10月30日(終了)
■追加開催 2019年11月27日(終了)
1 パワハラ対策の現状と課題
窓口設置(大企業、中小企業)、相談件数目安、無関心と過剰反応
2 カギを握る経営者・幹部の理解
組織の風通し、組織コミュニケーションと経営判断の関係
3 パワハラとセクハラの対応スキームの違い
「行為者の上司」がパワハラ問題解決のキーパーソン
4 厚労省マニュアルからみた『7つの準備』
人事部門が対応すべきこと(7つ)、社労士等による支援(3つ)
5 パワハラ新法と就業規則・規程策定のポイント
パワハラと判断できない場合の規定、監督責任の規定等
6 どのような研修が必要とされているか?
標準研修とポイント、ディスカッション、課題対応へのカスタマイズ
7 ケースからみた「対応のポイント」
相談対応のフローチャート確認、ケース対応のポイント
■出版記念 2019年8月5日(終了)
■追加開催 2019年8月23日(終了)
■追加開催 2019年9月9日(終了)
■追加開催 2019年10月30日(終了)
■追加開催 2019年11月27日(終了)
| ●管理職研修 | 15万円+税 | (90分) | |
| ●経営幹部講習 | 15万円+税 | (60分) | |
| ●パワハラ対策導入支援 | 20万円+税 | (合計4時間) | |
| ●対応相談・スーパーバイズ | 5万円+税 | (1回2時間) |
その他、社労士・人事担当者向け専門研修もお受けしています。
●管理職研修・一般社員研修 90分 15万円+消費税 (60分化も可能)
パワハラとコミュニケーションの関係を重視した研修を行っています。
「あれもダメ」「これもダメ」といった「べからず集」的なパワハラ研修の場合、上司が萎縮してしまうことがあります。上司がパワハラと言われることを恐れて、部下へのコミュニケーションを減らしてしまうことは、パワハラ問題の根本的な解決にはつながりません。
コミュニケーションを減らすのではなく、コミュニケーションを促進する観点からの研修を行っています。
上司向けには「パワハラと言われにくいコミュニケーション法」、部下向けには「パワハラを受けにくいコミュニケーション法」などを中心にしています。
コミュニケーションの向上は、パワハラの抑制効果を持つだけでなく、働きやすさや生産性向上にもつながります。
●経営幹部講習(経営者・幹部の方) 60分 15万円+消費税 (40分化も可能)
人事ご担当者からは「どうやったら上にわかってもらえるのか」という悩みをよくお聞きします。幹部の方の場合、一般社員とは視点が違うため、経営や生産性の観点が重要になります。また「短時間」というのもポイントです。
幹部講習は、短めのものをご要望されることが多いため、40分化も可能です。
内容は、全体像と主要ポイントに絞り、マネジメントやコミュニケーションとの関連にフォーカスしています。
忙しい経営者・幹部の方は、詳細を知ることよりも、できるだけ短い時間で、概要をつかむことが重要です。
仕事のできる経営者・リーダーの方の中には、A4・1枚の文書しか受け取らない方もいます。そこで、講習用のレジュメは、A4・1枚のみとし、事例やエピソードなどを交えてご説明します。
●パワハラ対策導入支援 20万円+消費税(合計4時間。2~4回に分けて合計4時間の訪問支援)
どんなパワハラ対策を導入していいかわからない場合の導入支援です。
厚生労働省のマニュアルなどをもとに何をすべきかをご説明します。

厚労省のマニュアル・ダウンロード。 |
まずは、厚労省のマニュアルをダウンロードしてお読みください。ただ「ページ数が多すぎて、どこが重要なのかよくわからない」という声が多いのも事実です。読んでもよくわからない、どう使っていいかわからないという場合に、重要ポイントを解説しながら導入支援をします。
就業規則そのものはお作りできませんが、社労士様向け研修もしておりますので、法令に沿い、かつ運用しやすい就業規則策定のポイントも解説します。
相談対応は、フローチャートやビデオ等も使いながらご説明します。
●スーパーバイズ 5万円+消費税(1回2時間。訪問支援)
その他、パワハラ対策・パワハラ対応に関する、様々なお困りごとのスーパーバイズ(外部の視点からの専門的な相談・助言)。
パワハラ対応は基本的には内部で検討することが望ましいですが、少し視点を変えたいというときに、外部の視点からのご助言をさせていただいています。「相談に乗ってほしいので、一度来てもらいたい」という場合などにも、ご対応しています(法律相談、医療相談を除く)。
*東京・名古屋以外の地域へのご訪問の場合は、別途、交通費・宿泊費等をご相談させていただきます。
*緊急的な場合を除いて、ご希望スケジュールは、1~2か月先以降をご呈示していただけると助かります。
*公務職場の方の場合は、ご予算等に応じてご相談いただければと思います。
contact17@stresscare.com
(恐れ入りますが、「contact17」を半角に直してご入力下さい)
(3営業日程度以内にご返信差し上げます。申し訳ございませんが、広告・ご案内等に関しましては、ご返信させていただいておりませんので、ご了承下さい。なお、stresscare.comからの受信ができない場合は、gmailなどからご返信させていただきます。)
<事業主の責務>
1 予防から相談対応までのパワハラ防止 措置義務
2 研修の実施等 努力義務
<役員・労働者の責務>
1 パワハラ問題について関心と理解を深めること 努力義務
2 他の労働者に対する言動に必要な注意を払うこと 努力義務
3 事業主の措置に協力すること 努力義務
すべての役員・労働者に、法律でパワハラ防止のための努力義務が課されました。
事業主の責務は、
■大企業 2020年6月1日施行
■中小企業 2022年3月31日までは、措置義務部分は努力義務
(中小企業の基準は、資本金額および労働者数など。小売業は50人以下、サービス業・卸売業は100人以下、その他は300人以下は中小事業主とされる。詳細は法令をご確認ください)
役員・労働者の責務は、企業規模に関係なく
■2020年6月1日施行
パワハラは、次の3つの要素が満たされたものと定義されています。
職場のパワーハラスメントの3要素
1.優越的な関係を背景とした
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
3.労働者の就業環境が害される(精神的・身体的苦痛を与える)
1.優越的な関係を背景とした
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
3.労働者の就業環境が害される(精神的・身体的苦痛を与える)
簡単な解説はこちらのページ 図解 職場のパワーハラスメントとは?
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法) 抜粋
第八章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等
(雇用管理上の措置等)
第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
4 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
5 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
(国、事業主及び労働者の責務)
第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
(助言、指導及び勧告並びに公表)
第三十三条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
2 厚生労働大臣は、第三十条の二第一項及び第二項(第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第八章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等
(雇用管理上の措置等)
第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
4 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
5 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
(国、事業主及び労働者の責務)
第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
(助言、指導及び勧告並びに公表)
第三十三条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
2 厚生労働大臣は、第三十条の二第一項及び第二項(第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
2011年7月~2012年3月 円卓会議
■職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議 各回議事録など
■職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ 各回議事要旨など
2012年1月
上記のワーキング・グループで取りまとめられた
■職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
(パワハラの定義案や、6つの行為類型などを提言)
2017年5月~2018年3月 検討会
■職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会 各回議事録など
2018年3月
上記の検討会で取りまとめられた
■「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書
この報告書を受けて、労働政策審議会(労政審)で議論。
2018年9月~2018年12月 労政審
■パワハラ防止について議論された労政審 各回議事録など
2018年12月
上記の労政審で取りまとめられた
■「建議」
この「建議」に基づいて、法制化。
<衆議院>
■衆議院での審議経過 インターネット審議中継
2019年4月25日 可決
■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(政府提出法案)
経過
■附帯決議(衆議院厚生労働委員会)
2019年4月25日 下記の野党提出法案は、いずれも審議の上、否決
1 業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案
経過
2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案
経過
3 労働安全衛生法の一部を改正する法律案
経過
<参議院>
■参議院での審議経過 インターネット審議中継
2019年5月29日 可決
■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案
本会議 投票結果
■附帯決議(参議院厚生労働委員会)
2019年6月5日 公布(官報)
■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
<関連>
■ILO 仕事の世界における暴力とハラスメントに関する「条約」
条約 投票結果
賛成 439 反対 7 棄権 30
(G7では、政府、労働側はすべて賛成。経営側は、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、カナダは賛成。日本とドイツの経営側は棄権)
■ILO 仕事の世界における暴力とハラスメントに関する「勧告」
勧告 投票結果
賛成 397 反対 12 棄権 44
(G7では、労働側はすべて賛成。G7の政府は、アメリカ政府は棄権、他の政府は賛成。経営側は、ドイツは反対。日本、アメリカ、イギリス、フランス、イタリアは棄権。カナダは賛成)
<ILOの定義>
the term “violence and harassment” in the world of work refers to
a range of unacceptable behaviours and practices, or threats thereof, whether a single occurrence or repeated, that aim at, result in, or are likely to result in physical, psychological, sexual or economic harm, and includes gender-based violence and harassment
(仮訳)
仕事の世界における「暴力とハラスメント」とは、
ある範囲の、受け入れられない行為や慣行、あるいはその恐れ。
一度限りのものも、繰り返されたものも。
身体的、心理的、性的、経済的な害を及ぼすことが目的とされた場合も、結果的にそうなった場合も、そうなりそうな場合も。
ジェンダーに基づく暴力とハラスメントを含む。
the term “violence and harassment” in the world of work refers to
a range of unacceptable behaviours and practices, or threats thereof, whether a single occurrence or repeated, that aim at, result in, or are likely to result in physical, psychological, sexual or economic harm, and includes gender-based violence and harassment
(仮訳)
仕事の世界における「暴力とハラスメント」とは、
ある範囲の、受け入れられない行為や慣行、あるいはその恐れ。
一度限りのものも、繰り返されたものも。
身体的、心理的、性的、経済的な害を及ぼすことが目的とされた場合も、結果的にそうなった場合も、そうなりそうな場合も。
ジェンダーに基づく暴力とハラスメントを含む。
■パワハラ防止 「組織コミュニケーション」の観点から (103ページ)

■「経営理論」から考えるパワハラ防止 (12ページ)

■パワハラ防止は軍隊の方針に適合するか? (13ページ)

■『上司が萎縮しないパワハラ対策 ―パワハラ新法への上手な対応―』目次 (加藤貴之著、日本法令刊)

以下は、1999年から2001年頃のビデオのため、映像に出てくるパソコンなどの情景はかなり古いですが、その点はご容赦いただければと思います。
ただ、対応に必要な内容は当時と変わっていません。初歩的な要素から専門的な要素に至るまで、そのままご活用いただくことができます。
『セクハラ相談 応対の基本』サンプル映像
『セクハラ相談 加害者ヒアリングの進め方』 サンプル映像
1999年発売の『セクハラ相談 応対の基本』は、日経新聞が出した最初のハラスメント関連ビデオで、また、ヒアリングの手法にカウンセリング的な考え方を導入したことで、おかげさまで、非常によく売れました。
カウンセリング的なヒアリングの手法を知りたい方に最適です。
日経新聞のご担当者が、タイトル名にこだわってくださり、「対応」ではなく「応対(おうたい)」としているところが最大のポイントです。
「対応(たいおう)」というと、どこか事務的な印象がありますが、接遇の意味も込めた「応対(おうたい)」とすることで、”被害者の気持ちに配慮する”という意図を込めています。
日本産業カウンセリングセンター理事長の野原蓉子先生が、数多くのセクハラ相談の経験から、カウンセリングのノウハウを盛り込み、当社加藤貴之がアメリカの相談ノウハウを調べて導入しました。
「エモーショナル」な視点と「ソーシャル」な視点は、アメリカのハラスメント分野で言われていたノウハウです。
カウンセリング的なヒアリングの手法を知りたい方に最適です。
日経新聞のご担当者が、タイトル名にこだわってくださり、「対応」ではなく「応対(おうたい)」としているところが最大のポイントです。
「対応(たいおう)」というと、どこか事務的な印象がありますが、接遇の意味も込めた「応対(おうたい)」とすることで、”被害者の気持ちに配慮する”という意図を込めています。
日本産業カウンセリングセンター理事長の野原蓉子先生が、数多くのセクハラ相談の経験から、カウンセリングのノウハウを盛り込み、当社加藤貴之がアメリカの相談ノウハウを調べて導入しました。
「エモーショナル」な視点と「ソーシャル」な視点は、アメリカのハラスメント分野で言われていたノウハウです。
2000年発売の『セクハラ相談 加害者ヒアリングの進め方』は、続編です。加害者とされる人のヒアリングは、非常に難しいものであり、多くのカウンセラーや人事担当者が頭を痛めていました。我々も特別なノウハウを知っているわけではなかったため、画期的なノウハウが入っているというものではありません。
「こういうケースがありますよ」というような意味での、ご参考にしていただければと思います。
このビデオは、タイトルを「加害者とされた人」か「加害者と申し立てられた人」とすべきではないかという点で、議論をしました。
ヒアリングの段階では、事実認定はまだされておらず、その時点で「加害者」と呼んでしまうのは間違いです。英語でも、alleged harasser(ハラスメントをしたと申し立てられた人)とされています。
しかし、ビデオのタイトルとして長すぎるということになり、大変申し訳ないのですが、タイトルは「加害者ヒアリング」とさせていただいています。
「こういうケースがありますよ」というような意味での、ご参考にしていただければと思います。
このビデオは、タイトルを「加害者とされた人」か「加害者と申し立てられた人」とすべきではないかという点で、議論をしました。
ヒアリングの段階では、事実認定はまだされておらず、その時点で「加害者」と呼んでしまうのは間違いです。英語でも、alleged harasser(ハラスメントをしたと申し立てられた人)とされています。
しかし、ビデオのタイトルとして長すぎるということになり、大変申し訳ないのですが、タイトルは「加害者ヒアリング」とさせていただいています。
2001年発売の『メンタルケアの聞く技術(アクティブリスニング)』は、話を聞くことの重要性を、事例を通して伝えていくとよいのではないかという観点から、企画されています。
カウンセリングの世界では、「聞く」という文字ではなく、「聴く」という文字がよく使われます。「心を込めて傾聴する」という意味で用いられています。
企業の管理職の方に「聴く」というレベルまで求めるのは、負担が大きすぎるのではないかということで、このビデオのタイトルは「聞く」という文字を使っています。
聞く技術は、ハラスメント予防においても重要です。多くのハラスメントは、「一方的なコミュニケーション」によって、双方の間に「行き違い」が起こることから始まっています。
ハラスメントやその深刻化を防ぐには「双方向のコミュニケーション」が重要です。「双方向のコミュニケーション」のためには、積極的に話を聞く「アクティブリスニングの技術」が活用できます。
カウンセリングの世界では、「聞く」という文字ではなく、「聴く」という文字がよく使われます。「心を込めて傾聴する」という意味で用いられています。
企業の管理職の方に「聴く」というレベルまで求めるのは、負担が大きすぎるのではないかということで、このビデオのタイトルは「聞く」という文字を使っています。
聞く技術は、ハラスメント予防においても重要です。多くのハラスメントは、「一方的なコミュニケーション」によって、双方の間に「行き違い」が起こることから始まっています。
ハラスメントやその深刻化を防ぐには「双方向のコミュニケーション」が重要です。「双方向のコミュニケーション」のためには、積極的に話を聞く「アクティブリスニングの技術」が活用できます。